プロテクトについて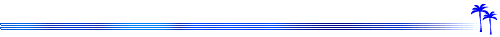 「TRYCUT2000のプロテクトって、どうなっているのでしょうか?」という ご質問をよくいただきます。よくあるのが従来使っていたマシンからの 乗り換えや、ディスクの故障などで他マシンに移行せざるを得ない場合 などですが、その他にも様々なケースが考えられます。ひとつのライセンス コードで一時的に複数のマシンで利用してしまう場合など、確かに動作はしても 気持ちが悪いというところのものはあるでしょう。一方、うっかり使って いただけだから、後から不正使用が発覚して請求されても困ると言う 場合もあるでしょう。これはTRYCUT2000だけではないと思います。 確かに、なんとなく気持ち悪いものです。 そこでTRYCUT2000のプロテクトというより、ここではプロテクト 全般の話をさせておいていただく方が良いと考え、特別に本ページにて 説明させておいていただくことにいたしました。一般的なPCユーザー にとっても、理解しておいていただいた方が良い内容でもありますので ご一読いただければ幸いです。
<プロテクトの目的> 世の中のプログラムが全てがフリーソフト(無償)であれば、プロテ クトという発想はないわけですが、たとえフリーソフトにしてもソフト ウェアの開発は莫大な時間(人件費)を消費します。ですから、どんな ソフトでも無償というわけには行かず、有料にすることで、その 収益を再投資して、より優れたソフトウェアとして磨きをかけてゆくこ とができます。 問題なのは、その代金の回収方法ですが、何もプロテクトがかかって いない落ちてるようなソフトでは、残念ながら誰も送金などしてくれま せん。(筆者はアミューズメント系のオンラインソフトで、プロテクト のないシェアウェアを公開したことがありますが、ユーザー数はTRYCUT などより多いのにもかかわらず1年間に1人ぐらいしか送金してもら えません。) やはりプロテクトをかけて送金してもらったらソフトを使えるようにする という仕組みが必要になります。また複数台で常時使っているのにもかか わらず1台しか登録していないケースなども同様です。
<プロテクトの種類> 一般的にプロテクトには、ハードプロテクト(シリアルポートやUSBポートに 装着)と、ソフト的にシリアル番号だけでプロテクトをかけるものが あるのはご承知のことかと思います。どちらかと言うとCAD/CAM /CAEソフトのように単価が高い(数十万円〜数千万円)ソフトに 関しては、前者が多く、OSやワープロ、またTRYCUTなどの廉価なプロ グラムの多くは後者の方法を取っています。特に前者は複数台数で同時に 利用する場合には非常に効果的に働きます。が、一方マシンの乗り換えや テスト的な一時使用などの柔軟性にはかける欠点があります。いずれに いたしましてもハードプロテクト自体、それなりにコストもかかるもの ですから、結局ソフト自体が廉価なものでは、そのような仕組みを 単独では持ちにくいというところがあります。
<プロテクトは完全か?> プロテクトのためにTRYCUT2000もハードプロテクトをかけるべきでは と良く言われることがあります。それではハードプロテクトというのは それだけ効果的と言えるのでしょうか?最近ではかなり巧妙なソフト ウェアもありますが、最終的には答えはNOと判断せざるを得ません。ハード プロテクトと言っても結局は、その認識部分をトレースしてソフトを書き換え るか、ハードキーの完全なコピー、もしくはエミュレーションを実現すれば 動作させることができるようになります。この手のプロであれば、いかなる 巧妙なプロテクトでも破ってみせるでしょう。また悪いことに半分趣味(腕自慢)み たいなところもあるところがなおさらチャレンジ精神をあおってしまいます。 今後はどうかわかりませんが、現在の有名なCAD/CAM/CAE系ソフトは、悪質業者に ほとんど全てプロテクトを破られています。 そういう意味ではソフトプロテクトも同様ですが、あまりにも安直なので 逆にターゲットになりにくいという面はあります。しかしシリアル番号の 流出はインターネット上では常態化しています。ですからソフト開発業者と しては、ハードプロテクトもソフトプロテクトも抑止力的なものでしかなく、 完璧なものはまず無理と判断せざるを得ないわけです。
<プロテクト破りに対する、行過ぎた対抗処置> このような背景もあり、ソフト業者は、プロテクト破りに対してあの手 この手と数年前から対抗処置を取ってきているのですが、いくらなんでも やり過ぎだという問題も起きたことがあります。 かなり前の話になりますが、日本のある優秀なシェアウェア 作家が、インターネット上に流出したシリアル番号に対して、対抗 処置を取るために、そのシリアル番号を入れてプログラムを動作させると 正常に動作しているようなフリをして、ディスク内のファイルを全部 消して行くと言うような仕組みを忍ばせたようで、非常に有名なソフト であったことから、不正使用も多く、これによってかなりの方々が被害に 遭われ、少し問題が大きくなりそうになったことがありました。 ただシェアウェア作家協会の同士の中では、いくら なんでもやり過ぎだという意見で集中砲火となり、その後オンラインソフト の中では、同様の事件は起きなくなったかと記憶しております。大変普及し 社会的貢献してきたソフトが、一転ウィルスに変身してしまったわけで、 いくら不正の取り締まりと言っても、やはりモラルの問題があるということ がソフトウェア開発者に衆知されたわけです。
<見えざるプロテクト> 昨今のようにインターネット常時接続や、社内LANや家内LANなど が復旧してきたことにより、見えざるプロテクトがかかってきたと言えます。 つまりこのような環境下ではコンピューターを使っていてプライバシーを 完璧に保護するというのは非常に困難になってきました。例えばOSである Windowsのアップデート機能にしても、マイクロソフト側からすればマシン の中の情報を調べるのはいとも簡単に行えるわけです。これは何もOSだけで なく、実行されるプログラムにとっては全てそういうことになります。 この部分も、少しモラルの問題もあるのですが、注意しておかなければ ならないのは、通常の市販プログラムでも、結構そのようなプライバシー? を自社に送ろうと動作している形跡を見かけることもあります。これは 明らかに不正使用のチェックをかけているのではと思われることがあります。 たぶん、不正使用を把握されていても黙認しているケースもあるかもしれません。 正当なライセンスで動作させている分には、特にやましいことはないので 、心配はないのですが、そもそもこのようなことを、されているということ自体は 別の意味で問題はあるかもしれません。(現時点のTRYCUT2000では、一部の例外を除き そのような動作は行っていません。)しかし、このような環境であることが、 不完全なプロテクトであっても、見えざるプロテクトとして不正使用を 抑制する力を持ちつつあるかとも思っています。 TRYCUT2000におきましても不正使用や不正ライセンスキーを把握しているものも ありますが、今後はモラルの点も考慮して、その時代に適合したレベルで 対処してゆきたいと考えております。何事も程度問題がありますが、 あくまでも不正使用者を見つけ摘発してゆくという方向に進んで行くのではなく、 不正使用ができない環境を目指してゆくということでしょうか。 少し曖昧な表現にさせていただきましたが、ご理解いただけますよう お願いいたします。 ※TRYCUT2000は、全ユーザー全マシンに対して全て異なる ライセンスコードを発行しています。
PS:
※世の中のプロテクトの最新動向としては、Windowsと同じくインターネット 経由による、ユーザー認証方式が主流になる可能性がありそうです。今後のTRYCUT でもユーザー認証方式の採用を踏まえ調査/検討中です。
|